打ち合わせの合間に車を走らせていたら、キウイの受粉作業に遭遇。キウイのオーナー制度を取り入れている東野さんの果樹園にて、キウイの花を撮影させていただきました。ありがとうございます!徳島市内の『Bar鴻kohno(コウノ)』さんのカクテルにも使われている人気のキウイ。収穫の時季(11月上旬~中旬)になると多くの人が村外から果樹園にやってきます。
2017年05月23日撮影
Kiwifruit (often shortened to kiwi), or Chinese gooseberry, is the edible berry of several species of woody vines in the genus Actinidia.The most common cultivar group of kiwifruit (Actinidia chinensis var. deliciosa ‘Hayward’) is oval, about the size of a large hen’s egg: 5–8 centimetres in length and 4.5–5.5 cm in diameter. Kiwifruit has a thin, fuzzy, fibrous, tart but edible, light brown skin and light green or golden flesh with rows of tiny, black, edible seeds. The fruit has a soft texture with a sweet and unique flavour.
Kiwifruit is native to central and eastern China, with the first recorded description dating back to the 12th century during the Song dynasty. In the early 20th century, cultivation of kiwifruit spread from China to New Zealand, where the first commercial plantings took place. It gained popularity among British and American servicemen stationed in New Zealand during World War II, and later became commonly exported, first to the United Kingdom and Australia from 1953,:followed by California in 1959.
From the late 20th century, countries beyond New Zealand initiated independent kiwifruit breeding programs, including China and Italy. As of 2023, China accounted for 55% of the world’s total kiwifruit production, making it the largest global producer.
キウイフルーツ(英: kiwifruit)は、マタタビ科マタタビ属の雌雄異株の落葉蔓性植物の果実である。また、マタタビ属のActinidia deliciosaを指して特にキウイフルーツとも呼ばれる。温帯の果樹で、秋に果実が実る。果実は産毛のような細かい毛が生えており、ビタミンCを多く含む。野生種のサルナシの近縁にあたり、中国に分布するオニマタタビ(シナマタタビ)からニュージーランドで改良されて作出された栽培品種であり、ニュージーランドの国鳥キーウィに因んで名をつけられている。
植物としての特徴
中国原産のオニマタタビ(鬼木天蓼、学名: Actinidia chinensis、別名:シナサルナシ)が、南半球のニュージーランドで改良されたもの。果樹としてなじみがあり、庭木としても見られる落葉性のつる性木本[10]。つるは全体的に褐色の粗い毛が多く、太くなると樹皮は縦にひび割れる。枝の随には隔壁がある[10]。花期は5 – 6月(日本の場合)。冬芽は褐色の毛に覆われていて互生し、隆起した葉痕上部の中に隠れて、先端だけが少し見えている半隠芽である。葉痕は円形や半円形で、維管束痕が1個つく。栽培
日本での商業栽培は温州ミカンなど柑橘類の余剰対策の転作作物として始まった。専門知識がなくても比較的簡単に栽培ができ、苗は一般向けにホームセンターなどの園芸コーナーで容易に入手できる。雄雌を1株ずつ植え、藤棚を使い蔓(ツル)を上手くはわせて栽培すれば、10月から11月頃には果実が収穫できる。よく成長した株の場合、一株から約1000個もの収穫を得ることもしばしばであるが、大量の結実は糖度が下がり酸が増加することで食味を低下させてしまう。表年・裏年もあるので、人工授粉と実の大きさがピンポン球大の頃に、摘果を行うことが望ましい。収穫後は30 – 60日程度の追熟をさせると食べられる。日本
日本ではニュージーランド産やチリ産、アメリカ産の輸入品が通年流通しているが国産品もあり、量が多くないが愛媛県、福岡県、和歌山県、香川県などで栽培されている。国産は11 – 4月ごろに出回る。なお、シマサルナシが、紀伊半島東南部を東限として、四国の太平洋岸、淡路島東南部、九州の沿岸地域、山口県の島嶼部、南西諸島に自生分布しており、国外では朝鮮半島南部の島嶼部、台湾にも一部自生が報告されている。絶滅危惧種に指定されており、キウイフルーツには無いポリフェノールを含有していることから、三重県熊野市や御浜、紀宝両町では、新たなご当地フルーツとして産地化を図っている。
・徳島県 – 徳島県の場合は、1981年の寒害によってミカン産地が壊滅的被害を受けた後に、代替作物として始められたものである。
佐那河内村、小松島市・香川県 – 「香緑」「さぬきゴールド」「さぬきエンジェルスイート」「讃緑」など品種開発を盛んに推し進める。また県と香川大学により開発された「さぬきキウイっこ」は、農地所有適格法人及びJAなどを通じて流通されている。
善通寺市、高松市、三豊市・愛媛県 – 栽培面積、生産、出荷量、販売額とも国内1位で、1970年代からミカン栽培からの転作によって産地が発展した。その経験を活かし、産地間で連携し、安定供給を図っている。ゼスプリによる契約産地の一つにもなっている。
松山市、西条市、大洲市、砥部町、伊予市、今治市などネコとキウイの関係
キウイフルーツの木の下で眠るネコ
キウイフルーツはマタタビ科マタタビ属の植物であり、マタタビラクトンがネコの鼻の奥にある「鋤鼻器」というフェロモンを感じる器官を通じ、ネコを興奮させるため、キウイフルーツの木にはしばしばネコが集まる。マタタビラクトンを嗅いだネコの反応は、床を転げまわる、走り回る、攻撃的になる、よだれを垂らす、眠くなるなどがある。特に去勢前のオスネコは、過剰に反応を起こすことがある。市販されているキウイフルーツに含まれるマタタビラクトンは微量であるため、キウイフルーツを食べてマタタビと同じ反応をするネコと、全く反応しないネコもいる。
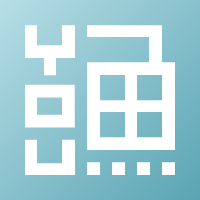


![【香川】川沿いをピンクに彩る80本の桜。湊川『河津桜ロード』 - [Kagawa] Kawazu Cherry Blossom Road](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49092-featured-120x120.jpeg)









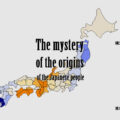



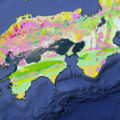
![【香川】春日川の川市 – [Kagawa] River market of Kasuga river](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/wordpress-popular-posts/49605-featured-120x120.jpeg)






![【徳島 7/6】1000m山の上。大川原高原のあじさいまつり – [Tokushima 6 July] Hydrangeas of Sanagochi Village](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/06/ajisai-sanagochi-150x150.jpg)









![【生誕102年 香川】彫刻家『流政之』 – [Kagawa] Sculptor Masayuki Nagare](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2019/04/nagare_matakimai-1-800x534.jpg)

![【小豆島 3/29-5/10】瀬戸内海を泳ぐ鯉のぼり『旧戸形小学校』 – [Shodoshima island 3/29-5/10]Carp streamers in the Seto Inland Sea. ‘Former Togata Primary School’](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/05/Carp-streamers_Togata-Primary-School-800x534.jpeg)

![【島根】出雲神話の舞台『稲佐の浜』 – [Shimane] Inasa Beach, the setting of the Izumo myth](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/07/inasa-beach_shimane_izumo-1-800x534.jpg)











![【香川】建築家・山本忠司設計、瀬戸内海歴史民俗資料館 – [Kagawa] “Seto Inland Sea Folk History Museum” designed by Architect Tadashi Yamamoto](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/Seto-Inland-Sea-Folk-History-Museum_Tadashi-Yamamoto-800x535.jpeg)
![【岡山】市庁舎から美術館へ。丹下建築から浦辺鎮太郎から受け継ぐ倉敷の名建築『倉敷市立美術館』 – [Okayama] The Kurashiki Municipal Museum of Art](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2025/08/panorama_kurashiki-city-museum_11-800x533.jpg)



![【香川 国の登録有形文化財】築100年以上の古民家『松賀屋』 – [Kagawa National tangible cultural property] “Matsugaya”, Traditional Japanese House](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/07/matsugaya_nio_mitoyo-800x534.jpeg)



![【女木島 8/2-3】島の神様に捧げるお祭り『住吉神社大祭』 – [Megijima island 2-3 Oct.] The shrine festival at Megijima island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/08/megi-island-festival-800x533.jpg)



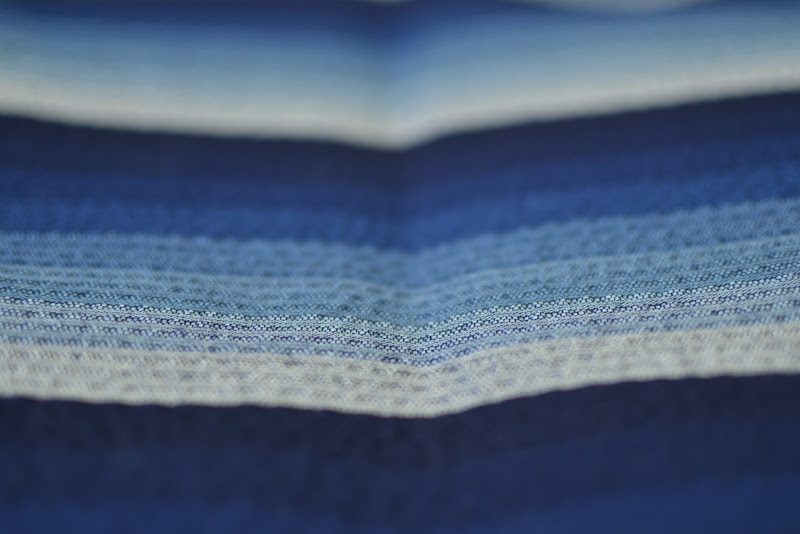

![【徳島 国指定史跡】前方後円墳をトンネルが通る!『大代古墳(おおしろこふん)』 – [Tokushima / National Historic Site] Ōshiro Kofun Ancient Tomb](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/11/oshiro-kofun-ancient-tomb_01-800x534.jpg)
![【香川】ぱしふぃっく びいなす – [Kagawa: Arrived Saturday 19 Nov.] Pacific Venus](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/11/pacific-venus-800x533.jpeg)


![【香川】毎朝焼き立て!高松のスコーン専門店『grain. (グレイン)』 – [Kagawa] Freshly baked scone “grain.”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/01/DSC_8980-1024x683-1-800x534.jpg)


![【香川 2025年9月頃】サンポート高松に外資系ホテルが開業予定 – [Kagawa Around Sep. 2025] New hotel will open in Sunport Takamatsu](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2022/06/sunport-takamatsu_hotel-800x533.jpeg)

![【愛媛】西条はそば処『西條そば 甲』 – [Ehime] Saijo Soba “KINOE”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/08/DSC00001-800x534.jpg)
![【高知】樹齢500年、霧の中のひょうたん桜 – [Kochi] Gourd‐shaped cherry blossoms](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/04/niyodo-river_sakura-800x450.jpg)

![【香川】甘い香り。いちご狩り スカイファーム – [Kagawa] Strawberry Picking “SKY FARM”](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2018/05/strawberry-800x534.jpg)

![【小豆島】みのりジェラート – [Shodoshima island] MINORI GELATO](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2021/06/MINORI-GELATO_Shodoshima-island-800x533.jpg)

![【香川】はざまのいちじく(無花果) – [Kagawa] Fig of Hazama, Mannou town, Kagawa pref.](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2017/08/fig_hazama_mannou-town-800x450.jpg)


![【香川】あの世へ向かう銀河鉄道のよう。与島の盆踊り – [Kagawa] Bon dance of Yoshima Island](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2023/08/yoshima_bondance-800x533.jpg)



![【香川】江戸そば 日月庵 – [Kagawa] Edo soba Nichigetsuan](https://yousakana.jp/wp-content/uploads/2020/12/Kagawa_Edo-soba-Nichigetsuan-800x533.jpg)











コメントを残す